01

2023年度 修士課程進学
(酵母発酵学社会連携研究部門)
石井 優人さん
「生物、化学」+「実験」+「楽しさ」=農2!!
私は、以下のような人に是非生命化学・工学専修(以下農2)にきてほしいと思います!
生物や化学、実験が大好きな人
農2では、食品や微生物、土壌、有機化学などなど生物、化学に関する非常に広い分野を学ぶことができます。さらに、3年生の学生実験では一年かけてそれら全ての分野の実験を行います。生物、化学好きまたは実験好きの人にはたまらない環境です!!
進路が漠然としか決まっていない人
農2では先述の通り、広い分野の学問を学んだ後でその中から興味のある分野を一つ選んで、研究室に配属された後その学問を深めることができます。まだ自分のやりたいことが決まっていない人でも、2、3年生の間に多くが自分の興味ある分野を見つけています!
人と関わるのが好きな人
農2は、人数が他の学科と比べ、非常に多いため多くの人と関わることになります。特に、3年生で一緒に実験をする仲間とは深い絆ができます。また、研究室に配属された後も研究室内での飲み会や学科内のソフトボール大会など数多くのイベントがあり、たくさんの友人ができることになります!!

私は現在ビール酵母の遺伝子の研究をしています。自分の生活に密接に関連するものについて研究ができるというのも農2の魅力かなと思います。
02

2023年度 修士課程進学
(食品生化学研究室)
廣 佳穂里さん
農2に入って良かった!
農2の研究とは?
農2というと農業?お酒づくり?というイメージが強いと思います。しかし、農2で数年間過ごした私が、農2の研究を一言で表すと、「社会実装につながる基礎研究」です。
農2と他学部との一番の違いは、研究成果をどのように応用するかだと思います。例えば私は、ヒトの脂質代謝機構やその破綻で生じる生活習慣病について研究していますが(これは医学部や薬学部、理学部でも行われています)、最終的には得られた研究成果をもとに新たな食生活を提示し、健康寿命延伸に貢献したいと考えています。このように、生物に関する基礎研究がしたいけれど自身の研究を直接社会に役立てたいと感じる人には、とてもおすすめの研究分野です!
農2だからこそできたこと!
また、農2には分野が様々な多数の研究室があります。3年生で各分野の専門性に触れた上で、幅広い選択肢から研究室を選べるため、真に自分の興味に合った研究室を選ぶことができます。私は今、日々研究に励みつつ専攻主催の五月祭を企画するなど、充実した楽しい毎日を送っていますが、これは農2に入ったからこそだと思っています。皆さんもぜひ農2でお待ちしています!

試験管内で培養できるミニ臓器、オルガノイドを培養しているところです。実験時間が長いなど大変なこともありますが、最先端の研究を自分の手で行えることに毎日ワクワクしながら取り組んでいます!
03

2025年度 修士課程進学
(生物制御化学研究室)
高野 日向子さん
多彩な研究内容で、自分の‘好き’を極めよう
生命化学・工学専修の魅力は多岐に渡りますが、その中でも特に知ってほしいおすす めポイントを2つ紹介させていただきます!
① 学べる分野の広さ
生命化学・工学専修に入ると、2年生の秋から分子生物学、食品科学、土壌・植物学、 有機化学、環境科学、微生物学など、非常に多彩な授業を受講することができます。私は初め土壌・植物学には全く興味がなく、大学受験でも化学物理選択であったため、苦手意識が強かったですが、その道のプロである先生方の授業は非常に興味深く、結局今では植物を研究テーマにしています。自分がもともと興味のあった分野の学びを深めるのはもちろん、全然興味のなかった分野にも挑戦できるのがいいところだと思います。
② 学科の人数が多い
生命化学・工学専修は、農学部の中で最も人数の多い専修で、文化祭の時にはみんなで協力して企画を作ったり、テスト前には勉強会をしたり、研究室対抗のソフトボール大会があったりと、楽しい学生生活が送れます。人数が多い分、研究室数も多く、さまざまな研究室の中から自分に最もあった研究室を選べるのは大きな魅力だと思います。

私はシロイヌナズナを使った植物ホルモンの研究を行っています。種から育てて一個の実験が終わるまで6週間ほどかかりますが、植物を育てるのがとても楽しく、毎日可愛がりながら研究しています!
04

2025年度 修士課程進学
(生物化学研究室)
永井 佑樹さん
充実度ナンバーワン!
農2はさまざまな方面で圧倒的に充実している学科です!これらの点がいいなと思ったら、来て後悔することは絶対にないです!
研究分野の広さ
このガイダンスブックを読んだらわかるように、農2は研究分野の範囲が圧倒的です。皆それぞれ全く異なる研究をしているため、実際に、自分とは違う研究室に進んだ友達と話していると、なんじゃそりゃ、となることもあります。二、三年生のうちに広い選択肢の中から自分の最も興味のある分野に出会い、四年生ではその方向に進める、というのがこの学科の魅力の一つです!
大人数
農2は人数が多いことも特徴の一つです。毎年60人から80人ほどが進学し、特に三年生での学生実験は一つの大きな部屋で班に分かれて行うためワイワイ楽しく、たくさんの仲間ができること間違いなしです!
五月祭
五月祭では、三年生では焼き鳥とビール、四年生では利き酒、修士課程でもさらに出し物をするのが恒例になっています。特に、利き酒は毎年グランプリを狙えるほど人気で、ここまで一丸となって出し物をできる学科はなかなかありません!
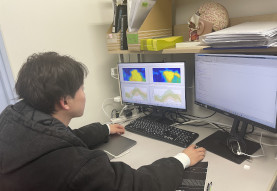
私の所属する生物化学研究室は、主に「匂い」の研究をしています。その中でも、私は特に「ヒト」を対象とし、色々な匂いに対する脳波の反応の違いなどを研究しています。
